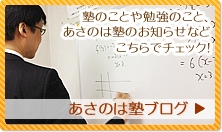2013,10,03, Thursday
知的発達に遅れはないのに、いざ学習にとりかかると、いろいろ問題が持ち上がる子どもたちがおり、前回はそのうち、学習障害(LD)と、注意欠陥/多動性障害(ADHD)を取り上げました。今回は、こちらもしばしば話題になる、高機能自閉症のアスペルガー症候群について記述します。
・自閉症の3つの症状
まず、自閉症(autism)とは、次の3つを特徴(ウィングの三つ組)とする発達障害であり、100人に1人の割合でいると考えられています。
1.社会性の障害
この記事には続きがあります▽
あさのは塾便り::勉強・子育てなど | 03:56 PM | comments (x) | trackback (x)